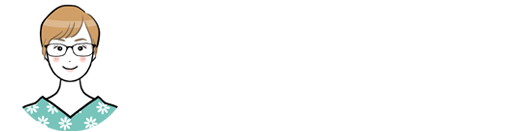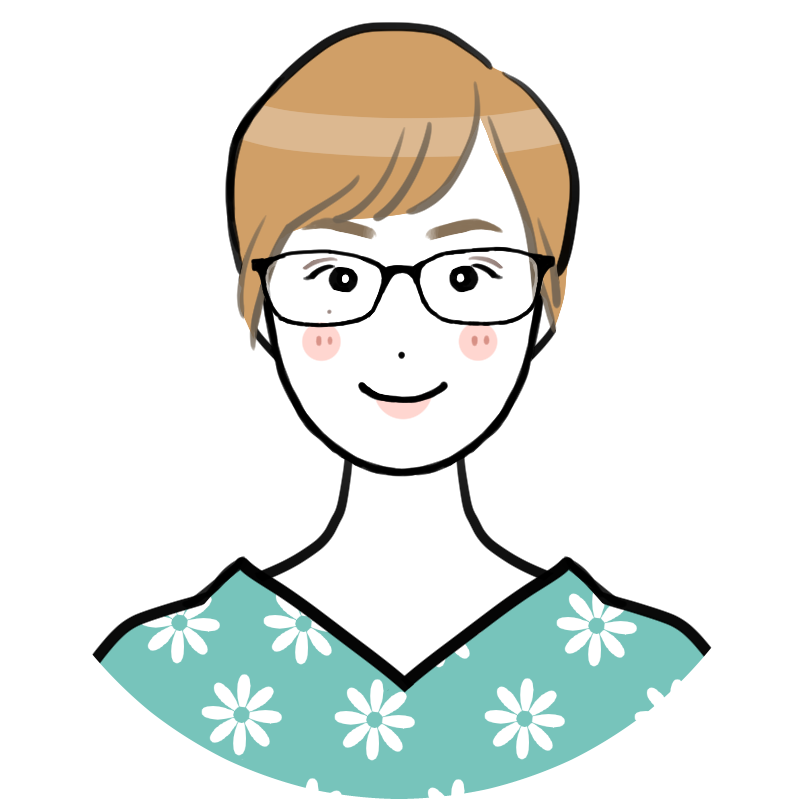
スポンサーリンク
目次
保育参観当日の格好
- 動きやすい、汚れてもいい格好
- 日焼け止めを塗る
- 虫除けスプレーをかける
当日は砂場遊びなどを一緒にすることもあるので、汚れてもいい格好がおすすめです。裾を引きずらない濃い色のズボンをおすすめします。子どもの目線に合わせてかがむことも多いので、あまり股上の浅いジーンズだとお尻が見えてしまうので注意。
保育園についてからは塗っている時間もないので、天気のよい日は出かける前に塗っておくのがおすすめです。
夏には必須です。わたしの時は保育園で貸してもらえましたが、事前に家で塗布したほうがおすすめです。蚊にさされた痕は、なかなか黒ずみになってしまった色素が抜けないので……。
保育参観当日の持ち物
- エプロン2枚(遊ぶ用、給食用)
- ハンドタオル(手拭き用)
- 外靴
- 帽子(暑い日)
- 給食代
- 三角巾
- マスク
室内遊び、外遊び用の汚れてもいいエプロンと、給食の際につけるエプロンの2枚が必要です。
保育園で園児は各自でタオルを持参してきているので、自分用のハンドタオルが必要です。
泥や砂で汚れてもいいように、外靴の準備がおすすめです。
日差しが強い場合もあるので、念のため持ってきてください、と保育園からの持参品リストの中に書かれていました。
0歳クラスは離乳食なので、量も味見程度の量しかないため料金はかかりませんでした。
1歳クラスになると、大人も食べられる量の給食になるので、参観には別途給食代が発生します。
お釣りのないように準備しておくとスマートです。
ちなみに子どもが通っている保育園では、1食340円でした。
スポンサーリンク
保育参観当日の注意
現金はできるだけ少なくすること
財布にはクレジットカード類が入っているので、保育園には持ち込まないようにしました。
わたしのおすすめは、給食代がすぐに取り出せるように茶封筒などに入れておいて、あとはのどが渇いた時のために数百円を別で持参するくらいで十分です。
荷物は最小限にすること
保育園は空いているスペースがありません。
わたしの当日持参したバッグは、子どもが触らないようお昼寝用の布団を入れているクローゼットに一旦しまいました。
軽いエコバッグに必要最小限のものだけを詰めて保育参観に向かいましょう。
保育参観に参加してわかったこと
変装はしなかった
マスクとか、伊達メガネとか、母と分からずに新任の保育園の先生として紛れ込むのかな、とドキドキしていたのですがそんなこともなく、「今日は○○ちゃんのお母さんが参観にきてくれています」と朝の会でふつうに紹介をしていただきました。
子どもたちが人見知りしない
0歳クラスからお迎えなどで、見知っているクラスメイトが多いためか、子どもたちが人見知りせずにどしどし膝に乗ってくること。
右膝と左膝にそれぞれ座られ、我が子が嫉妬して怒るほどでした。(笑)
参加スケジュール
- 9:00 登園
- 0~2歳クラス合同の朝の会
- 外遊び
- シャワー
- 11:30 給食
- 帰宅
0~2歳クラスまでの子どもが大集合しました。
先生がピアノをひいて、一緒に手遊びをしたり歌をうたったり体操をして過ごします。
先生が話している最中は、手遊びができるおもちゃが配られたりと始終子どもが飽きないようテンポよくすすめていましいた。
0歳クラスの赤ちゃんが泣いてしまった場合は、保育士の先生が抱き上げてあやしていました。

朝の会が終わると、子どもたちは各自クラスに戻っておむつを替えて水分補給をします。その後、先生に虫除けを塗ってもらい、保育園の黄色い帽子をかぶって外遊びをします。
ちなみに帽子のてっぺんにはクラスごとに異なるカラーを縫いつけてあります。
例:0歳クラスは黄色
園庭は0~1歳クラス、2~5歳クラスで遊ぶエリアが分かれています。(怪我防止のため)
0~1歳クラスの園庭には、砂場とおままごとのできる遊具があり、子どもたちは好きな遊具で遊びます。わたしは砂場で一緒に遊びました。
初夏で天気の良い日だったので、砂、汗の汚れを落とすために園庭にあるシャワーを使いました。
シャワーを浴びた後はすぐにおむつと着替えがあるので、先生と連携して子どもを受け渡して拭いて、着替えさせて……とわたしも保育士並に活躍しました。(笑)

外遊び後なので、しっかり手を洗った後、先生が濡らした自分の手拭きで各自手を拭いて、給食前にお茶で水分補給をします。
子どもたちが椅子に座って絵本を各自読んでいる間に、先生は給食の準備をします。
給食は、子どもと同じメニューを先生と一緒にいただきます。
給食は野菜を細かく刻んだメニューで、ヘルシーで美味しかったです。
デザートにはメロンが出てラッキーでした。
食べながら、子どもたちの食べる様子を見て、なかなか食べない子どもには促して食べさせます。
アレルギー食が必要な子どももクラスに数名いて、先生は配慮しながら対応していました。
ご飯を食べた後は、昼寝に入ります。
先生が寝かしつけに入っている間に、自分の子どもを引き取って帰ります。
その時に、保育参観を体験してみて感じたことなどを書くアンケートを先生に渡されました。
その場の記入ではなく、帰宅後書いて保育ノートに提出する形のアンケートでした。
スポンサーリンク
夫も参加してみた
「子どもが普段こんなふうに過ごしているのか」と新鮮な驚きがあったので、夫にも参加を促してみました。
夫の場合は、ちょうど保育園の避難訓練日にあたってしまい、ずきんを被って近くの小学校へ子どもたちと一緒に避難をしたそうです。
子どもの普段の様子はわからなかったようですが、先生方がてきぱきと避難準備をしているのを見て、信頼を強めたようです。
1家庭の参加回数の確認
これは保育園によって違うのですが、わたしの場合は、年度で1家庭2回までの参加でした。
また、参加者も1名までの受け入れなので、夫婦で参加することはできませんでした。
あんまり保育参観が楽しかったので、実は3回目を申し込んでしまったら、参加当日にこのルールが発覚し、参加できないことになってしまいました。
保育園側からも申し訳ないということで、その日は正午まで子どもを預かってもらい、家で家事をする時間に当てました。
もし複数回申し込む場合は、わたしのようにならないためにも、念のため保育園に確認した方がよいかもしれません。
スポンサーリンク
まとめ
子どもが保育園でどのように普段過ごしているのか、知るためにも保育参観はとてもおすすめです。特に、夫にも参加してももらって、保育園への親しみや理解が深まりました。
子どもが保育園で気に入っているおもちゃや絵本を実際に見て確認することができたので、自宅でも同じものを揃えました。
保育園と家庭での「連続した」保育という点でも、保育参観への参加はおすすめです。